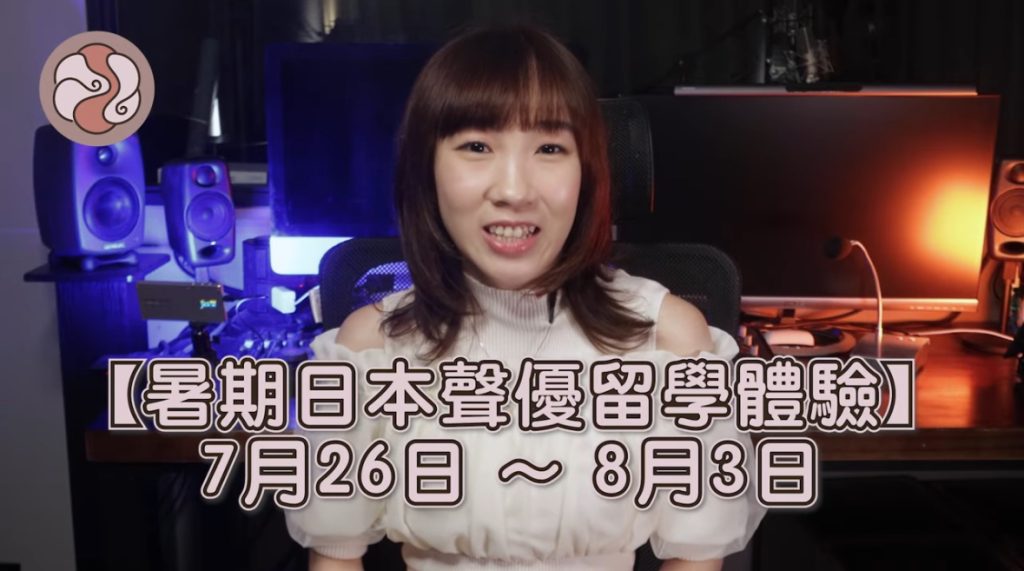昨日から広島です。

乗換案内のアプリによく出てくる広島の「府中」。
この標識を見上げながら、
日振協の中国・四国地区対象のセミナーを一緒にする、
評議員の山田先生と共に、会場の広島YMCAに。

当たり前のことなんですが、
ここにもこんなにたくさんの日本語教育関係者が!
文科省の調整官も東京から来てくださり、皆皆皆…で。
とにかく、認定目指して皆で駆け抜けようの会。
また参ります。
そして、一夜明け。

起きて、シャワーあびて、FBをちらっと開いたら、
なんと!小林先生が広島にいると書いてある!
インターカルトの先生を経てアメリカに渡って30有余年。
今、奥さんのベッツィーさんと日本旅行中、ということは
知っていましたが、まさかの至近距離に。
で、急ぎ支度して、歩いて6分の小林ご夫妻がお泊まりの
ホテルのロビーでしばしの再会を果たしました。
小林先生は、インターカルトの養成と先生としての先輩、
縁は続くよどこまでも。