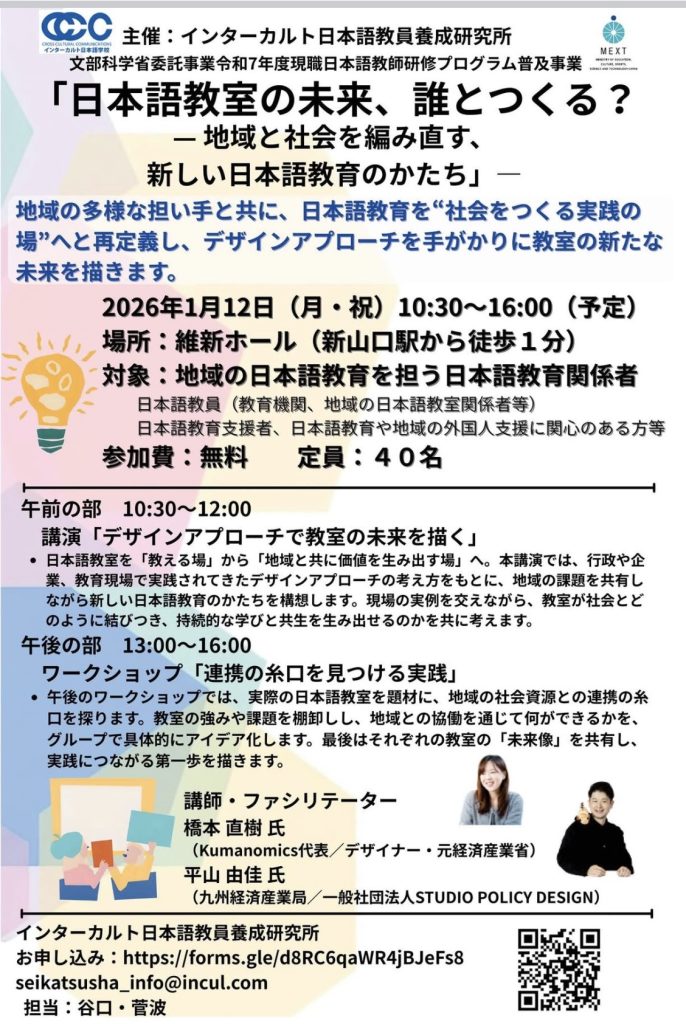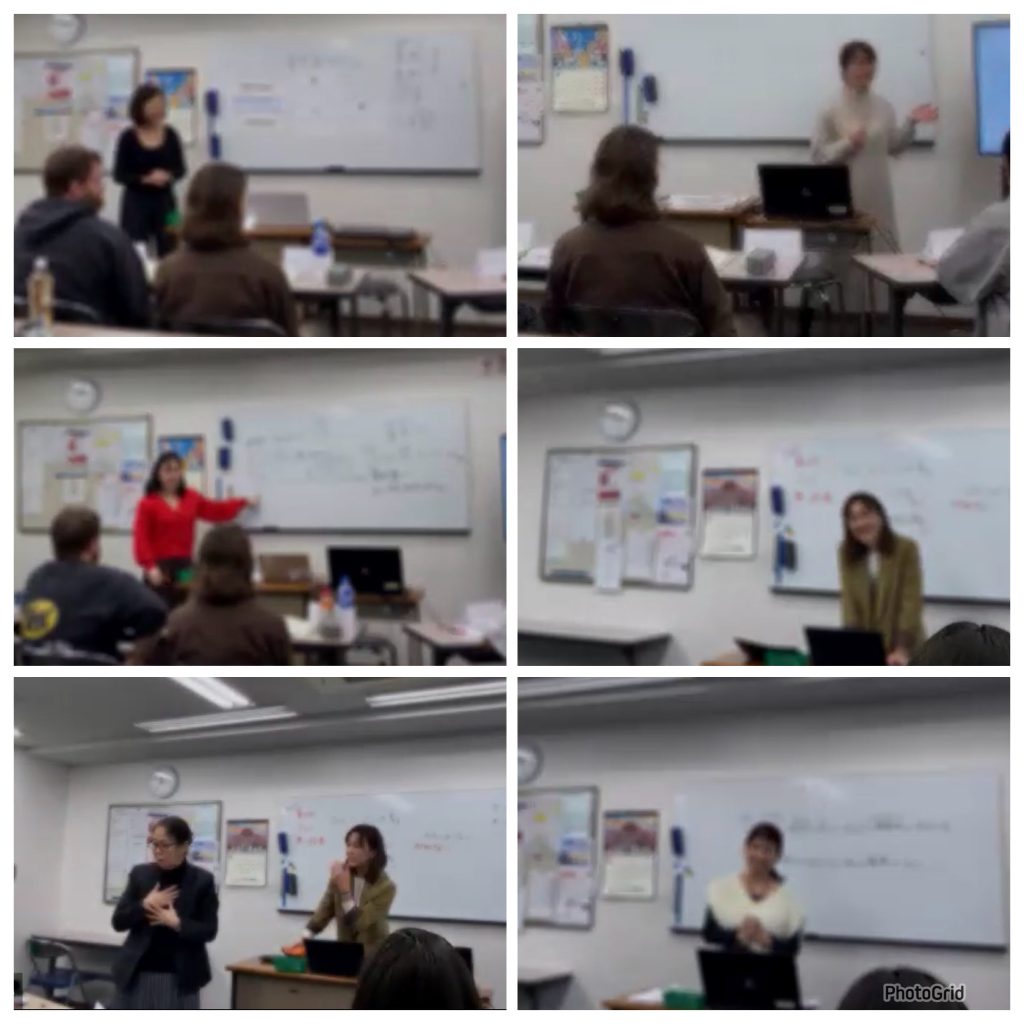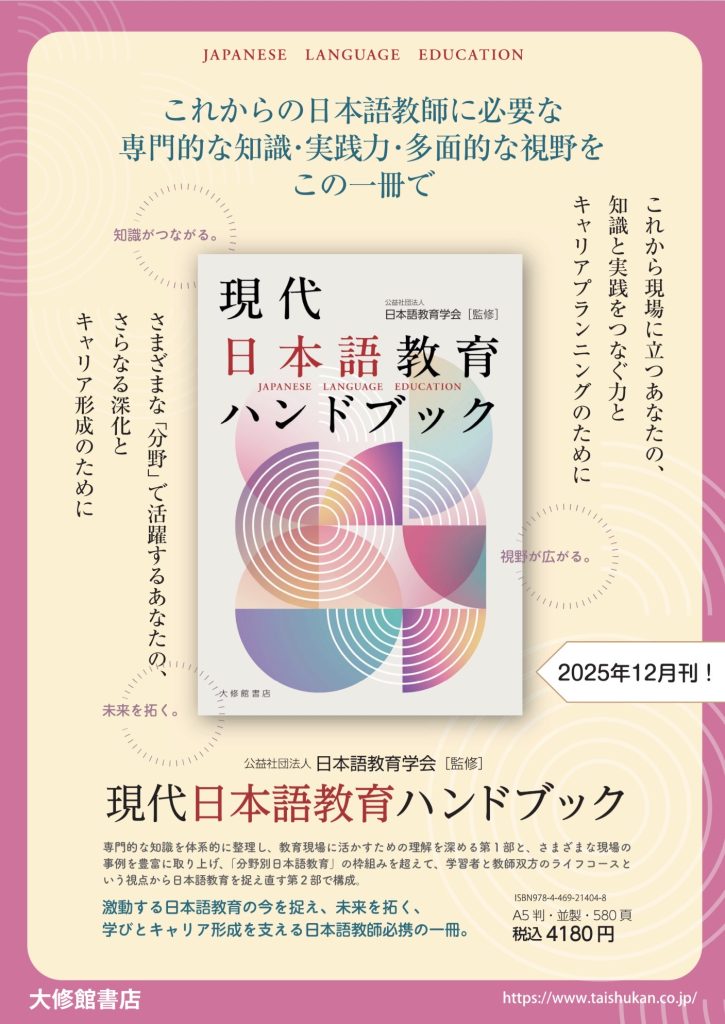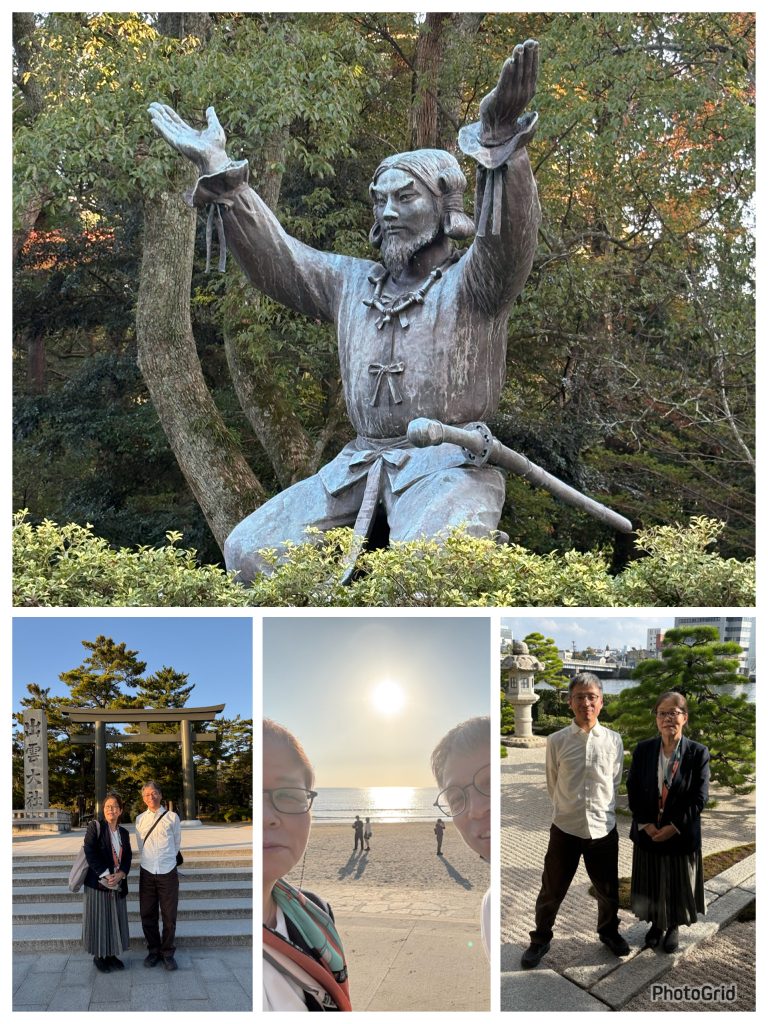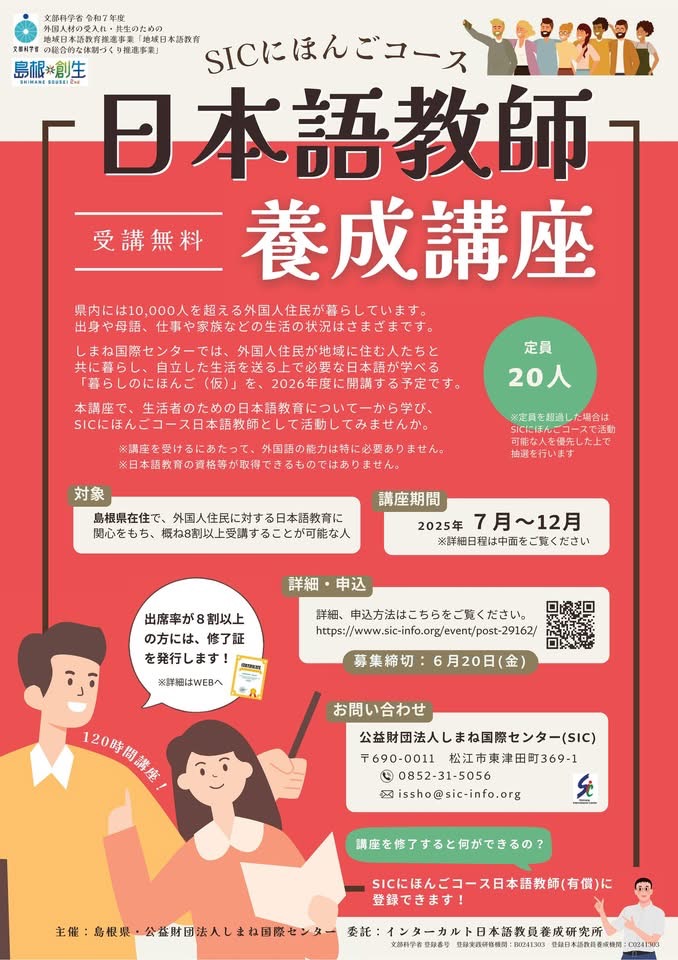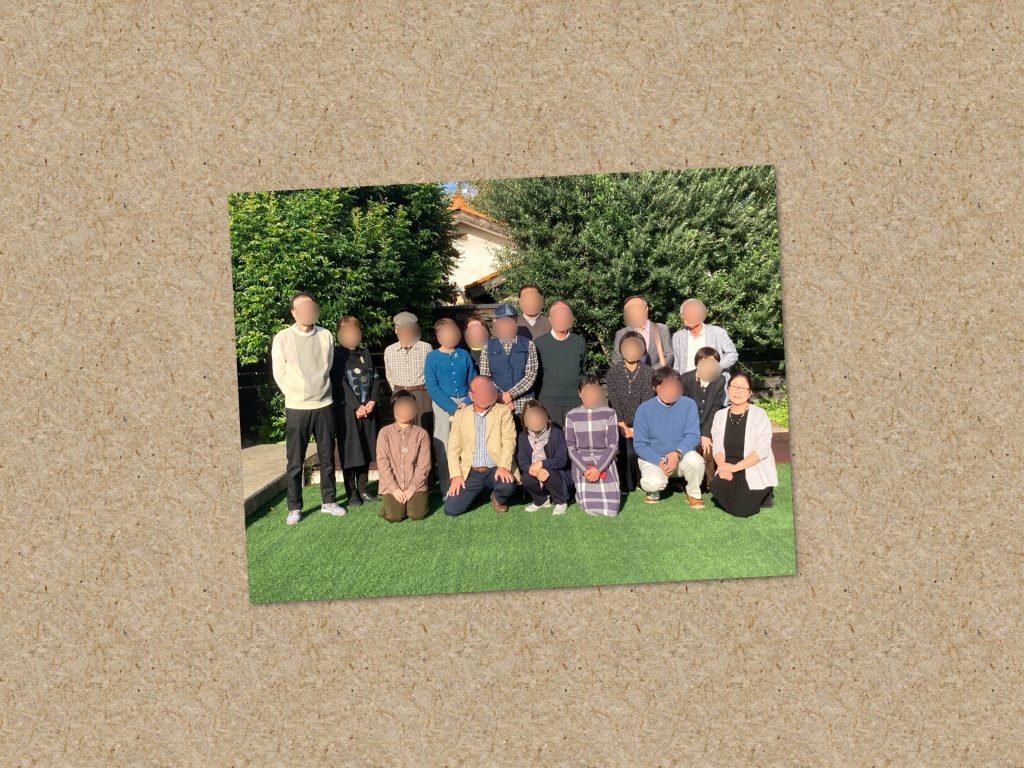本日、東京商工会議所台東支部の新年賀詞交歓会でした。
懇意にしている北区の学校の先生からの紹介で入会して数年、
初めて参加しました。
会場の浅草ビューホテルは、インターカルト創立40周年の時の
大同窓会をしたところ。来年はもう50周年です。光陰矢の如し。
台東支部の会員さんには有名どころがたくさん在ります。
上野動物園、今半、バンダイ、松屋浅草、東天紅は私の結納の場所。
去年、新会長になられた仁木会長さんは、リーリーとシンシン
(パンダです!)を上野動物園に呼んだ立役者のお一人で、
今月中国に返還されるシャオシャオとレイレイの名付け親なのだと。
挨拶の方たちの口からも、パンダの話題が出てくる出てくる。
ああ、台東区はパンダなんだなと。
私にとっての台東区は浅草です。
故郷、足利からは東武伊勢崎線の終点浅草が、東京の入り口。
「浅草こそが東京」で育ったような、です。
インターカルトが台東区に引っ越してきてから18年です。
どうしてだか、観光・サービス分科会の評議員を拝命してます。
ちゃんと貢献もしなくちゃなと思った今宵でした。